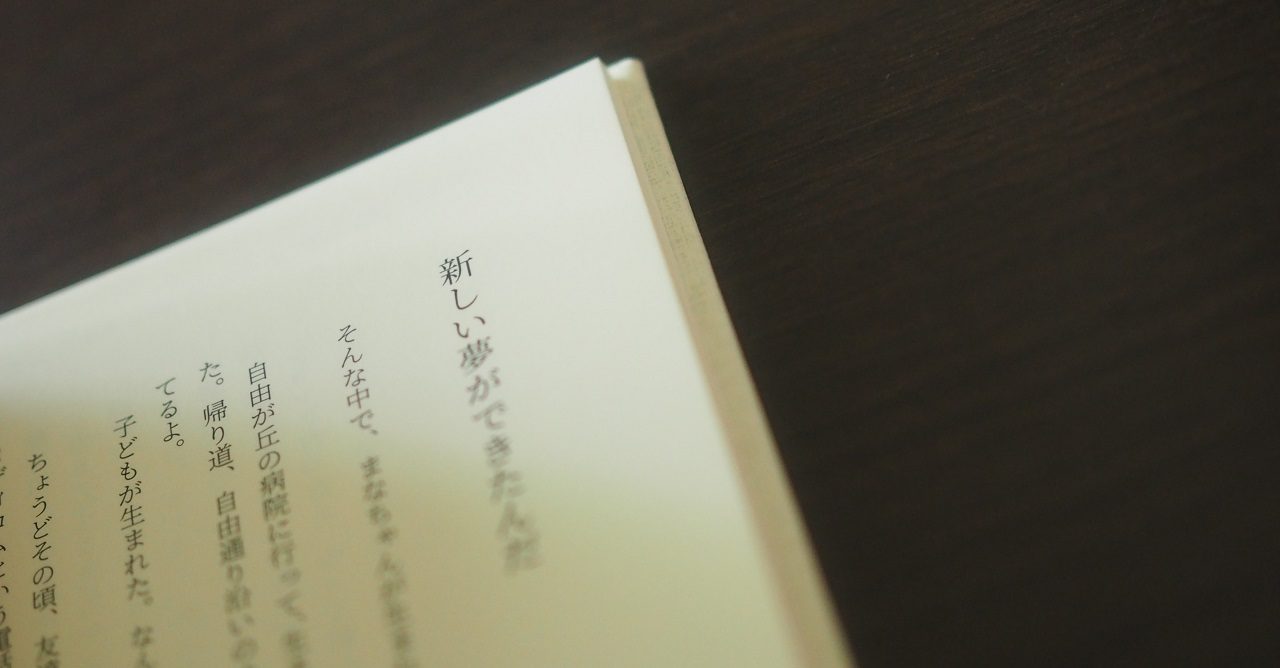『このひより』運営チームのウィルソンです。
この事例紹介では、サービスを利用いただいた方々の反応や、実際に仕上がった本の内容、私たちがインタビューをさせてもらうなかで感じたことなどをお届けしていきます。
今回ご紹介するのは、私の父の話。還暦に贈ったインタビューで、断片的にしか知らなかった父の人生をじっくりと聞きました。ライターとして、贈り手である娘として、今も忘れられない1冊が手元に残っています。
あくまで一つのギフトの形としてお読みいただきながら、「自分だったら、こんな場面で贈りたいな」とイメージを膨らませていただければうれしいなと思っています。
『このひより』で父の人生をまとめたい
私の父は、53歳にして経営していた会社を手放し、ずっと目標にしていた早期引退の夢を叶えました。
ずっとがむしゃらに働いてきた父。引退してようやくのんびりするのかと思ったのも束の間、そこから急速に元気がなくなっていくのが、傍から見てもわかりました。
仕事一筋だった方が定年を機に社会とのつながりや存在意義を失ってしまう、いわゆる「燃え尽き症候群」かもしれない。そう思った私は、仕事の他にやりたいことを探したら、と父に提案しました。
ただ、父自身も新しいことに挑戦してみたものの、なんだか熱意を持てない様子。「この年齢で何ができるんだろう」「自分にはもう打ち込めるものは見つからないかもしれない」と弱気になっていきました。
娘として、そんな父を見るのはつらかった。私のなかの父は、常に前を向き、困難を乗り越えてきた人だったから。

幼い頃から父に断片的に聞かされていた武勇伝は、数多くありました。地元・長野でのやんちゃなエピソード、歌手を目指して上京したときのこと、挫折を経て自分の会社を立ち上げたこと。子ども心に「お父さんはすごい人生を送ってきたんだ」と思っていたし、自慢の父でした。
それが、今まで成し遂げてきたことを忘れたかのようにしぼんでいく。お父さんはこれまですごいことをしてきたじゃないか、それを思い出してほしいと思ったのが、『このひより』で彼の本を作るきっかけでした。歩んできた人生をひとつの物語として読み返すことができたら、父の中で何かが変わるんじゃないか、と。
長野のやんちゃ坊主は、どのような道を辿って大人になったのだろう。田舎でお蔵に閉じ込められる少年のイメージと、自分で立ち上げた会社を早期退職し、今は都内で妻と愛犬と気ままに暮らす彼――つまり私の父の姿は、まだイマイチ繋がらない。
『この日』――2019年9月5日。私は、そんな父の長い長い物語の始まりを追いかけ始めた。
一緒に振り返った「この日」
「どこから話す? お父さんの人生は濃いからね、長くなるよ(笑)」
インタビューの日、そこにいたのはいつもよりテンションの高い父。最初から聞かせてよ、と生まれ育った長野のことや幼少期の話から聞いていきました。
初めて買ったレコードは、歐陽菲菲(オーヤンフィーフィー)の『雨の御堂筋』。歌を歌うのは、ずっと好きだったね。
小学生の時から、お母さんが働いていた日本生命の社員旅行や慰労会で歌を披露していたっけ。三善英史、クール・ファイブ、郷ひろみ、野口五郎……。とにかく歌うことは楽しいなって思ってた。中学生の時は、西城秀樹にハマってたな。
好きな歌手、ハマっていたこと、バイト先での話、そして普段なら会話に登ることがない初恋や元彼女のことまで。
父もここまで根掘り葉掘り聞かれたことはなかったでしょう。「どうだったかなあ……」と記憶をたどりながら、少し自慢げに話す嬉しそうな表情が印象的でした。
話を聞きながら、ぼんやりとしかイメージできていなかった10代・20代の父の姿や生活が、言葉とともに鮮明になっていくのを感じていました。当たり前ですが、それは私が生まれる何十年も前の話。
そこには私の知らない父の人生があり、葛藤や悩み、喜びが詰まっていたのです。

そして、父の視点から見た、私の誕生も。つらい挫折を経験した直後だったことを、このとき初めて知りました。
そんな中で、まなちゃんが生まれた。
自由が丘の病院に行って、生まれたばかりのまなちゃんに会った時、すごい幸せな気持ちになった。帰り道、自由通り沿いのカウンターしかない小さな居酒屋で、ひとりでお祝いしたのを覚えてるよ。
子どもが生まれた。なんとか働かなきゃいけない。そんな気持ちにさせられたね。
子どもは、親の人生のすべてを知ることはできません。自分が生まれるずっと前、父が若かったころの話は新鮮でありながら、ますます父を身近に感じるものでした。
インタビューの場だったからこそ聞けた、父の言葉がたくさんあります。聞くことができてよかった、妹にも早く聞かせてあげたいな。そう思いながら、こぼれ落ちそうな父の武勇伝を必死にメモしていったのでした。
人生を振り返った彼に何が起きたか
インタビューを終えてみると、父はどこかスッキリした顔をしています。目に力が宿った、以前の父に戻ったようで、少し背筋がしゃきっと伸びたようにも見えました。
今日、こうやって振り返ってみると、色んなことをしてきたなあ。熱中していることがすごく好きだから、良い人生だったんだろうと思うよ。
でも、そんな僕の人生もいよいよ最終章って感じだね、まなちゃん。「終わりよければすべてよし」っていうのもあるからさ。これから、人生の最終章に何をするか、考えてみるよ。
その後まもなく、父から「やりたいことが見つかった」と連絡が入ったのです。
人生を振り返り、大切な記憶を掘り起こしてみる。自分にとって何が大切で、自分はどんな人間だったか。そんな棚卸しのような機会が、父には必要だったのかもしれません。
60年、途方もない長い時間です。それを必死で駆け抜けてきた人が、一息ついたり、改めて自分の大切にしているものを見つけたり。私が想像していたよりも大きな役割を「インタビュー」は持ちうるんだと感じました。
そして、そんな父の人生の棚卸しに「娘」として同席し、ともに60年を振り返ることができたのは、私にとっても忘れられない日となりました。
孫、ひ孫、またその孫までも
これまで私が人生に迷い悩んだとき、父からもらう言葉が道標になることが多かったのを覚えています。だからこそ、断片的にしか聞いてこなかった父の人生を1冊の本にすることは、ライターであり、娘である私がずっとしたかったことでもありました。
父という人間の人生は、たしかにそこにあった。一生懸命に生き、葛藤し、成長し、小さくとも多くのことを成し遂げて、今の父がいる。それをしっかりと父の口から聞き、彼の言葉が綴られた本は、これからもずっと残っていきます。
昭和35年から、令和2年の『この日』においてもまだ、彼は進んでいこうとしている。
時間は前にしか進まない。だから、彼は前を向くのだ。
「宝物だ。ありがとう」
完成した本を渡したとき、他に言葉が出ないのか、ぽつりと一言、父は言いました。
「私も一冊ほしい」
隣で涙目の妹がそう言って笑い、それからは父の人生について家族で話しました。「このとき大変だったね」「自分だったらどうしたかな」。ページをめくりながらそんな話をする時間もまた、家族にとってかけがえのないものでした。
まだ小さい私の子どもたちや、いつか生まれるかもしれないその子ども。彼らは父の口からは武勇伝を聞けないかもしれないけれど、この本があれば、誰でもいつでも彼の60年に出会えるのです。